猫たちと私
五年付き合った彼氏と、二時間ほど前に別れた。原因は相手の浮気。一年ほど前から何となく気づいてはいたけれどずっと知らないふりをしてきた。理由は単に修羅場的なことになるのが面倒くさかったからだ。
けれど三時間ほど前、大学の友達と飲みに行った先で別の女といちゃついている彼氏とバッタリ遭遇してしまった。付き合い始めよりも彼に対する愛情は大分薄らいでいたため、引導を渡すのは案外簡単だった。
慌てふためく彼氏に平手打ち一発。付き合い始めた頃に貰った指輪を薬指から引っこ抜いて、相手の飲んでいたビールジョッキの中に落として終わり。それでさよなら。
ずっと胸につっかえていたものが無くなってせいせいした私だったのだけれど、友人たちはそれを"傷ついているけれど無理をして気丈に振舞っている"と取ったらしい。
奢るから飲みに行こう!と友人に腕を引かれその後3軒ほど梯子し、私も半ば自棄になって飲みなれない日本酒なんかをガッツリと飲んだ。
気がつけば終電間際の時刻になり、心優しい友人たちの励ましを受けながらも岐路に着いたのだった。
火照る顔に春先の冷たい風が心地よい。
酔い覚ましに少しぶらついて行こうと近所の児童公園に足を向けたのが、そもそもの間違いだったのかもしれない。
人気のない公園のベンチに腰を下ろして空を見上げれば、雲間からぽっかりと丸い月が顔を覗かせている。そうか、今日は満月だったのか。月に向かって左手をかざし、もう何も無い薬指を見つめながらそんなことを考えていると、何処からとも無く動物鳴き声が聞こえてきた。
「猫?」
子猫だろうか。頼りなげな鳴き声は一つではない。
声のするほうへ足を向ければ、ダンボールの中で粗末な布に包まって子猫が二匹。身を寄せ合うようにしてそこにいた。二色のつぶらな瞳が怯えたように私を見ている。捨て猫だろうか。夜目には判別つきづらかったけれど、恐らく茶色と黒の毛並みのよい、しかし飼い猫ではないらしく首輪はつけていない。
春とはいえ、夜から明け方にかけてはまだまだ冷え込む日が続いている。
このままここに置き去りにしていたら寒さに弱って死んでしまうかもしれない、なんて考えた私だったのだけれど、本当は。彼氏と別れ何処となく物悲しさを覚えていたのも事実で、何か温もりが欲しかったのかもしれなかった。
「一緒に来る?」
手を差し伸べて訊ねれば、二匹の仔猫は答えるようにみゃぁと鳴く。
仲のよい子猫を引き離してしまうのは可哀相で、私は二匹を大切に抱きかかえると家に連れて帰ったのだった。
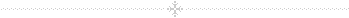
私の住んでいるマンションはペット禁止ではないから、管理人にばれないようにと気を使う必要もなく、子猫を抱えたまま意気揚々と玄関の扉を潜った。
子猫たちは腕の中でじっと大人しくしている。二匹を一度リビングのソファにおろすと冷蔵庫の扉を開けた。
牛乳は子猫に飲ませてもいいんだったろうか。パックを取り出しながら首を傾げ、しかし動物に対しての知識の薄い私に是非はわからず、使っていない皿にほんの少し乳白色のそれを注いで子猫たちの下へ戻った。
「飲む?」
二匹の前に差し出すと、子猫たちはおずおずと顔を近づけて鼻を動かし、小さな舌でちろちろと飲み始めた。愛らしいその姿に思わず笑みが綻ぶ。
「可愛いなぁ」
動物と触れ合うなんてそういえばいつ振りだろう。幼稚園か、小学校低学年か。その辺りの頃に柴犬を飼っていたのが最後だったと思う。名前はコロといってやんちゃな男の子だった。くるんと巻いた尾っぽをパタパタと振りながら、よく私のスカートの裾に食らいついてはスカートを駄目にしてしまっていた。言うことを聞かない我侭なところもあったが、それでも可愛い弟分で、コロが死んだときには大泣きをしたものだ。
「みゃぁ」
小さな鳴き声ではっと現実に引き戻される。
回想に耽っていた間にか子猫たちは牛乳を飲み終えていたようだ。二対の瞳が私をじっと見つめていた。
「今日はもう寝ようか」
二匹の小さな頭を交互に撫でてそっと抱え込む。軽いけれど確かな温もりが抱き上げた腕から伝わってきて思わず頬が緩んだ。
寝室に入って電気をつける。子猫たちを何処に寝かそうかと考えて、ベッドから少し離れた羽毛クッションの上におろした。大きめのサイズだから二匹を乗せてもどちらかが転がり落ちてしまうことは無いだろう。それだけだと少し寒いかもしれないと思って、ローチェストの引き出しからバスタオルを一枚取り出して二匹の上に被せてあげた。
しばらくもぞもぞと動いていた子猫たちが大人しく丸くなる様子を見届けて、手早く着替えを済ませる。シャワーは明日の朝浴びることにしよう。
「おやすみなさい」
電気を消して、二匹に向かって声をかける。
みゃぁと応えるように二匹の子猫の声が聞こえた。
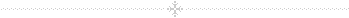
翌日、寝ぼけ眼で起き出してきた私は子猫の姿が無いことを訝り寝室を出た。そのままリビングに繋がる扉に手をかけたまま呆けた表情を浮かべる。リビングからはそれはそれは美味しそうな食欲をそそる匂いが漂ってきていた。けれどここで一つ疑問が浮かぶのは、私は一人暮らしであって、朝食を作ってくれるような人間が存在しないということだ。
はて。知らないうちに友達や家族がやってきた…なんてことはまずないはずだ。友達はともかくとして、家族はみんな数年前に他界してしまっている。
なら泥棒だろうか。…いやそれはないな。人の家でわざわざ料理をしていく泥棒なんて聞いたことがない。
見れば分かるか。わしゃわしゃと寝癖だらけの髪をかきあげて扉を開けた先にいたのは、見覚えのない二人の青年だった。
「あ、おはようございます」
私の登場に気づいて亜麻色の髪の青年が振り返る。彼の手にはフライパンとフライ返し。そして私がおきっぱなしにしてあったエプロンをつけていたのだけれど、柔和な雰囲気の彼にそれはやけに似合っていた。
対してソファで寛ぎの体制をとっていたのは黒髪の青年だ。亜麻色の髪の青年の言葉にぐるりと首を巡らせて微笑を浮かべる。おはようと挨拶をされて思わず返事をしてみてから、 いやいや可笑しいだろうと目いっぱい首を振って額に手を当てた。
人の家で勝手に寛ぎさも当然のように料理をする君たちは一体誰ですか。そもそもどうやって入り込んだんですか。家主の登場にも一切驚いた様子を見せないのは何故だ。
「あのー…どちら様?」
迷走する思考の中何を言おうかと散々迷った末、それだけでも口に出来た私を誰か褒めて欲しい。
亜麻色の髪の青年はキラ、黒髪の青年はアスランと名乗った。聞いた話によれば、彼らは昨日の夜私が酔った勢いで拾ってきた二匹の猫なのだという。元々は一応人間だという彼らだが、ひょんなことから新月と満月になると猫に変化してしまう体質になってしまったらしい。
は、そんな馬鹿な話とキラが作ってくれた悔しいぐらい美味しい朝食を口にしながら唸る私に、やっぱり信じられませんよねとあまり困った様子も無くキラが言った。
だって突拍子が無さ過ぎる。素直に信じる人間の方が可笑しいというものだ。
「そりゃねぇ、猫が人間になったり人間が猫になったりなんて聞いたことないもの」
「それにしては随分警戒心が薄いな」
アスランの言葉に私はあっさりと頷いてみせる。
「うん。だって君たち悪い人には見えないし」
悪いことする人だったら私に見つかった時点で真っ先に逃げ出してるか、もしくは襲い掛かって来ていると思う。男二人に女一人。どちらが弱いかなんて考えるまでも無く分かりきっている。
そう言えば二人は顔を見合わせて苦笑した。変わり者だと思ったのだろう。大丈夫、自覚はある。そうでなければ初対面の人間とこんなにのんびり朝食など摂っていない。
「食事に毒を仕込んでるとか考えないんですか?」
パクリとスクランブルエッグを口に入れたところで手を止める。まさか入れたんですかの意味合いを込めてじっと菫色の瞳をにらむと、彼は入れてませんよと笑いながら首を振った。こっそり胸を撫でおろし、空になった皿の上にフォークを置いた。
ちなみに今朝食をとっているのは私だけであって、二人の前には湯気の立つマグカップが置かれているだけだ。どうせだから一緒に食べればいいのにと勧めたのだが申し訳ないからと断られ、一人だけ食べているのも気が引けた私は二人に心ばかりのホットミルクを渡したのだった。凄く微妙な顔をされたのだけれど、だって猫と言ったらミルクではないか。
そんなホットミルクは先ほどから二人に口を付けられることも無く、寂しげに湯気を立てるばかりである。
「まあともかく。君たち二人はこれからどうするの?」
そもそも帰る家はあるんだろうか。思ったままの疑問を口にすれば、二人はもう一度顔を見合わせて首を振った。ああ、やっぱり。あればこんなところにいつまでもいないだろう。そう思ったのだが、しかし彼らは少し意外なことを口にした。
「あるにはあるが…今はまだ帰れない、な」
「僕たちとても遠いところから来たんです。だから帰りたくても帰れないというのが現状です」
何やらとても複雑な事情がありそうだ。猫になる体質を持っている時点で十分に複雑といえばそうなのだろうけれど。
ふむと小さく唸って、行儀が悪いと思いつつテーブルに頬杖をつく。
「つまり…帰れるようになるまでここに置いて欲しいと、そういうわけね?」
「まあ、簡潔に言ってしまえば」
彼らの言わんとしていることを察して訊ねれば、二人は控えめにだが確かに頷いた。
さてどうしたものか。
女の一人暮らしに男の同居人、それも初対面に近い二人である。常識的に考えると無い。まず有り得ないだろう。しかし彼らが本当に昨日の夜私が拾ってきた猫であるとするならば、そのまま出て行けというのはあまりにも無責任なことのように思えた。重要なことなので もう一度言う。本当に猫であるならば、である。
思わず頭を抱え込んだのは仕方のないことと言えるだろう。
「あー……うん。まあ、あれですよ。君たちが本当に猫だというのなら、ね? 私が拾ってきたのだから責任持って面倒見ようとは思うけれど」
君たちが猫だという明確な証拠はあるかと問えば、彼らは困ったように首を傾げた。
「証拠になるかどうかは分かりませんけど…」
「まあ何かあるのならどうぞ」
促して、キラが言った「証拠になるかどうか分からない話」に私は顔を真っ赤にさせてもういいですと両手を突き出した。
「ごめんなさい私が悪かったです。どうぞ思う存分我が家と思って寛いで下さい」
良いのかと訊ね返すアスランに、私は無言のままに頷いた。
キラが言ったのはなんと昨日私が身につけていた下着の色だった。何でそんなこと知ってるの!? と思わず問い質せば、昨日の夜僕たちの目の前で着替えていたので、と飄々と答えられてしまった。熱の篭る頬を押さえて俯く。穴があったら入りたいぐらい恥ずかしい。
予定外の同居人を抱え込むことになったことに加え、初対面の男共に下着姿までさらしてしまうだなんて。
一生の不覚だ。しかし女に二言は無いのである。
「じゃあ改めて宜しくお願いしますね」
「宜しくな」
「はぁ、宜しくしたくないけど、しょうがないからね。宜しくお願いします」
そんなこんなで珍妙な同居人との同居生活が始まったのだった。
――――――――――――――――――――――――――――――――
思いついて30分かそこらで書いた話。加筆修正は勿論加えてあります。
名前変換一個もない上に続くようで続かない。
とりあえず終わっとけ(笑)
H23.05.05